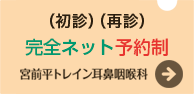【台湾鉄道旅②】第6話🚃雨の日はローカル線がちょうどいい
[ 公開日: 2026/2/14 ]
~「行かない場所」から決める旅のトリアージ~
☔ 旅のはじまりは、朝5:30の判断から
目が覚めると、窓の外はあいにくの雨だった。旅も後半に入り、右足の親指の状態を考慮する必要がある。前日はサンダル履きで台湾を一周したが、この雨ではそうもいかない。靴を履いて長時間歩くことは避けたい。
条件がそろっているからこそ、この日は「行く場所」を決めるのではなく、「行かない場所」を先に確定させるトリアージから始めた。九份や故宮博物院は歩行距離が長すぎるため、今日のリストからは外す。有名かどうかではなく、身体の現実と天候を優先する。消去法で残ったのが、駅から街が近く、歩行距離を短く設計できる内湾線だった。
7:40にホテルを出発。台北駅から新竹までは、あえて客車タイプの自強号を選んだ。機関車が客車を引く、昔ながらのスタイルだ。最新鋭の電車とは違う、どこか「許容される空気」がある。指定席に先客がいても、券を提示すれば穏やかに解決する。そんな時間の流れが、今日の自分には心地よかった。

🚃 新竹駅から内湾線へ
新竹駅でまず乗り込んだのは、六家(ろっか)行きの電車だ。ここは「内湾線へ行くための前段」であり、まずは途中の竹中駅を目指す。六家は高鉄(新幹線)との接続駅でもあり、生活の動線が機能的に整えられている。

この新竹から竹中までの区間が、この日一番の「試練」だった。車内の冷房が、12月末とは思えないほど猛烈に効いているのだ。台湾の鉄道には「車内は常に冷えていなければならない」という暗黙のルールがあるかのようで、思わず肩をすくめた。(なお、本線の自強号は極めて快適であり、この極端な冷気はローカル線区間ならではのものだった)。
数分で到着した竹中駅は、高鉄側への枝線が分かれる分岐点になっている。ここで内湾行きのディーゼルカーへと乗り換えた。
🛤️ 沿線に眠る「過去の熱量」と縁起物の駅名
竹中で乗り換えると、列車は非電化区間へと入り、景色は一気にローカル色を帯びる。 走り出してしばらくすると、縁起の良すぎる駅名が目に飛び込んできた。「栄華(えいが)」。名前の響きに反して、そこは驚くほど小さく静かな無人駅だった。この名前と実態のギャップが妙におかしくて、一人で小さく笑ってしまった。

沿線最大の主要駅、竹東(ちくとう)に到着すると再び空気が変わる。ここで私の目を釘付けにしたのは、ホームにある「24両編成」という停止位置目標だ。 現在の旅客列車ではまず出会わない数字だが、この路線はかつてセメント原料の輸送で賑わった貨物が主役だった。今目の前にある広大な設備は、かつての産業を支えた熱量の「記憶」なのだ。
さらに進むと、合興(ごうきょう)駅でまとまった数の観光客が降りていった。ここはかつて廃止の危機にあった際、ある夫婦の思い出の場所として保存を直訴されたエピソードから「愛情車站(愛の駅)」として親しまれている有名スポットだ。駅舎そのものが目的地となる賑わいを車窓から眺めつつ、列車は終点を目指す。
終点の一つ手前は、先ほどの「栄華」と対になる「富貴(ふうき)」駅だ。「栄華から富貴へ」。そんな言葉遊びのような駅名の並びを楽しみながら進むうちに、終点の内湾が近づいてきた。

🏔️ 警告看板に突きつけられた「19」の数字
内湾駅に到着。滞在時間は約70分。寄り道として楽しむには理想的なサイズ感だった。ここは客家(ハッカ)文化が息づく街であり、駅のすぐそばに老街が広がる。日本人にはまだ馴染みが薄く、日本語も英語もほとんど通じない。だが、その「放っておかれる感じ」が、今回の旅で一番心地よかった。
駅前には白い梅の花が咲き、地元の観光客が熱心に写真を収めている。まだ12月なのに「梅」。さすが南国・台湾だ。

街の象徴である内湾吊り橋へ向かったが、あいにく閉鎖中だった。傍らの警告看板には、戦慄する事実が記されている。 「統計によれば、この水域では20年間で累計19件の溺死事故が発生している」 この具体的な数字の提示は、観光地の華やかさの裏にある自然の厳しさを物語る。医師として「生命は一度きり」という言葉を重く受け止めつつ、橋は渡らず、老街へと引き返した。


🍢 100台湾元(≒500円)以下の幸せ、食べ歩きの老街
老街には家族経営の店が並び、作りすぎていない空気感が心地いい。財布に優しい「買い食い」を楽しみながら歩く。
特に外せないのが、この地の名物である「野薑花粽(ワイルドジンジャーのちまき)」だ。一口頬張ると、野薑花の花や根を練り込んだという爽やかで高貴な香りが鼻に抜け、脂っこさのない上品な味が広がる。小ぶりなサイズも、トリアージ中の胃袋にはちょうどいい。

炭火で焼かれた黒豚のソーセージは、日本のものとは違う独特の甘みと八角などの香辛料が際立つ、まさに台湾ならではの味だ。

さらに、タロ芋のモチモチしたお団子「芋粿巧(オークェイキャウ)」の素朴な甘さが際立つ。これら100台湾元(≒500円)以下の幸せを拾い集めるように味わった。
自分へのお土産には、天然素材の木の実で作られたキーホルダーを選んだ。一つひとつ個体差がある手作りの温もりが、雨の内湾の記憶を閉じ込めてくれる気がした。
🚃 前面展望が描く「一期一会の物語」
帰りは新竹への直通列車に乗った。ディーゼルカーの最前列、前面展望ができる特等席には年配の男性が先に座っていたが、私が日本人だと分かると、席を譲ってくれた。結局、二人並んで流れる景色を眺めることになった。

窓の向こうには、単線の線路が吸い込まれるように続いていた。急峻な山肌を削り、無理やり鉄路を引いた「切り通し」の崖。先人の苦労が岩肌から伝わる一方で、医師としての視線は災害のリスクをも感知する。この緊張感は、前面展望ならではの体験だ。

竹中駅までの約1時間、英語での会話は途切れなかった。彼とは竹中で別れることになったが、別れ際にツーショットを撮り、名刺を渡してLINEを交換した。彼が見せてくれた満面の笑みとサムズアップは、厳しい車窓の景色に、人間味という温かい色を添えてくれた。

🏰 歴史の門、新竹駅を診察する
12:43、新竹駅に戻ってきた。1913年完成、日本人建築家・松ヶ崎萬長が設計したこの駅舎は、ドイツ・ネオルネサンス様式を基調としたバロック様式の傑作だ。
駅舎を外から眺め、その端正な姿をじっくりと「診察」する。日本統治時代に建てられた西洋建築としての威厳と、百年の時間を経た赤レンガの質感。歴史を纏った建物の佇まいが、慌ただしかった一日の呼吸を整えてくれる。

🚃 莒光号、いま乗っておくべき理由
この後の莒光号への乗車は、あらかじめ狙い定めた選択だった。事前に時刻表を精査し、「これに乗る」と決めて捕まえに行ったのだ。
1970年の導入以来、55年にわたり親しまれてきた莒光号だが、車両の老朽化による置き換えが進んでいる。(注:その後、2028年末までの運行終了が正式発表された)。希少になっていく客車列車に、いま乗っておきたい。そんな旅人としての直感が私を動かした。

客車ならではの、機関車に引かれて動き出す際のがらりという衝撃は健在だ。電車にはない重厚な手触りが足の裏から伝わる。駅弁を広げ、特有の走行音をBGMに食べる時間は、何物にも代えがたい贅沢だった。列車が台北を過ぎ、終点の先、七堵へと近づくにつれ、旅の目的は移動から「記録」へと昇華していった。


🔧 仕組みが景色になる瞬間
15:09、七堵駅に到着した。ここへ来たのは、莒光号でしか見ることのできない、電気機関車の付け替え作業をこの目に焼き付けるためだ。
前後に機関車を配置する自強号の客車列車とは違い、この莒光号は終着駅に着くたびに機関車を一度切り離し、反対側へと回って連結し直すという「手間」が今も生きている。連結器が重なり、大きな音を立てて再び一本の列車になる。その無骨で力強い仕組みが、そのまま旅の景色になる。観客は私一人だけだったが、鉄道という巨大なシステムが発する鼓動を、最も近くで感じた時間だった。

⚓ 基隆は「また今度」
本当は鉄道の歴史が始まった場所、基隆へ向かうつもりだった。しかしホームの移動で間一髪間に合わず、疲労感と雨を見て、深追いはせずホテルへ戻る決断を下す。全部行かないのも旅の醍醐味だ。「台湾はまた来るから」と思える余裕が、朝のトリアージを正解へと導いてくれた。
16:30、ホテルサンルート台北に帰館した。夕食は昨日も訪れたお気に入りのミシュランの店「黄記魯肉飯」をテイクアウトし、これまた行きつけの果物店で買ったフルーツを並べる。台北の定宿を拠点に、馴染みの店をリピートする。それは、この街で「住むように旅をする」ことの象徴だ。


雨で、旅は後半で、足のこともある。 行かなかった場所を先に決めたら、行き先は自然に残り、すべてが一本の線に繋がった。 今日は「判断」を積み重ねた先に、納得のいく観光が成立した一日だった。